第63回教育科学研究会全国大会・武蔵野集会
第63回教育科学研究会全国大会・武蔵野集会
(略称: 教科研武蔵野集会)
主催 教育科学研究会・教科研武蔵野集会実行委員会
後援 武蔵野市教育委員会
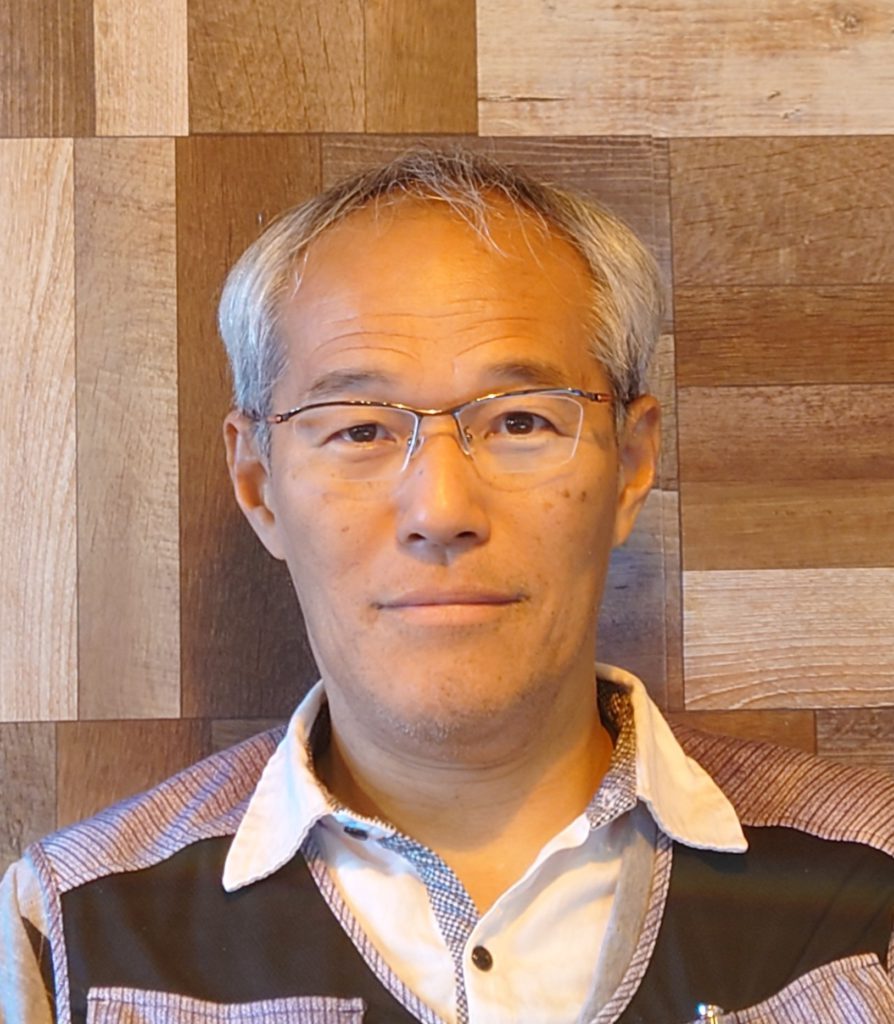
武蔵野集会 実行委員長からのメッセージ 横田誠仁
今年の教科研全国大会は、成蹊小学校で行うこととなり、武蔵野集会という名称で行うこととなりました。
成蹊小学校は、大正自由主義教育の旗手と呼ばれた中村春二先生の創られた学校です。「自由主義教育とは」ということを回顧する機会でもあって欲しいと思います。
また、小学校での開催ということで、現場の雰囲気を感じていただきながら、「子どもたちに伝えたい文化の享受」というものが何なのかを語り合える機会としていただければと思います。
その中で、今後の学校のあるべき姿を語り合えたらと思いますので、ご参集ください。

教科研委員長からのメッセージ 片岡洋子
教科研大会は特定の教科や領域だけでなく、幅広く教育について考えられるのがよいという感想をいただきます。今年も分科会世話人や実行委員会が、様々な切り口から今日の子どもと教育について考える企画を準備しています。
「はじめのつどい」の記念講演は作家の落合恵子さんです。落合さんは1976年、表参道に、子どもの本の専門店「クレヨンハウス」をオープンし、子どもの文化を豊かにするおとなたちの活動を支えてきました。その「クレヨンハウス」が、2年半前に吉祥寺に移転して、成蹊小学校のご近所になりました。この機会にぜひクレヨンハウスにもお立ち寄り、本だけでなく、自然素材のおもちゃやオーガニック食品もお楽しみください。
落合さんは1980年代から女性の視点で性加害を告発するなど、小説やエッセイで、沈黙させられる人の声を言葉に紡いで発信してきました。また多くの文化人・知識人の方々と一緒に、日本国憲法が掲げる反戦・平和と民主主義を守り、実現する活動を担ってきました。不正義への怒りを暴力ではなく言葉で伝えることをずっと私たちに教えてきてくださった落合さんの言葉に、ご一緒に耳を傾けましょう。
テーマ
ともに生きられる社会と教育を求めて
開催日
2025年 8 ⽉ 6 ⽇(水)、7日(木)、8 ⽇(金)
会場 ☆上履き・靴袋をご持参ください☆
成蹊小学校
https://www.seikei.ac.jp/elementary/
東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1
アクセス 詳しくは↓クリックしてください
https://www.seikei.ac.jp/elementary/information/access.html
*地図アプリを使う場合は「成蹊大学正門」に設定してください。
大学正門を入って、右側通路を進むと、右手に小学校があります。
*「成蹊小学校」で検索すると正確なルートが表示されない可能性があります。ご注意ください。
スケジュール
| 6日(水) | 10:00~12:00 | 教科研講座(対面のみ) |
| 13:30~17:00 | はじめの集いと記念講演(対面・オンライン) | |
| 18:00~20:00 | 交流会 | |
| 7日(木) | 9:30~17:00 | 分科会(対面・オンライン) |
| 17:15〜18:30 | 教科研総会 | |
| 8日(金) | 9:30~12:00 | 教育問題フォーラム(対面・オンライン) |
| 13:00~15:00 | おわりの集い(対面・オンライン) |
参加費
| 教職員(常勤) | 一般(保護者・市民・退職者など) | |
| 全日参加 | 5000円(会員割引 500円) | 4000円(会員割引 500円) |
| 1日参加 | 3000円(会員割引 500円) | 2000円(会員割引 500円) |
| ○学生・院生 全日・1日とも 1000円 ○高校生以下 無料 | ||
| 交流会4000円 ※学生・院生2000円 | ||
<第1日目 8月6日(水)>
13時30分〜17時
はじめの集い & 記念講演
対面・オンライン併用
13時30分~14時45分 はじめの集い
武蔵野集会実行委員長 あいさつ 横田誠仁
教科研委員長あいさつ+基調報告 片岡洋子
大会実行委員会企画 「寄り道していいんだよ」
わたしたちはいま、大人も子どもも、寄り道しないようにルートからはずれないように縛られてはいないでしょうか。いまの子どもを取り巻く現状を語り合い、子ども達の「自分色」がきらきらと輝くような世界を見つけていきませんか。
15時~17時 記念講演(質疑応答含む)
講演者 落合恵子さん (作家・クレヨンハウス主宰)
演題 「それぞれが自分色に」
ダイバシティなどと言葉だけは上滑りになっていますが、その実態は? わたしたち、ひとりひとりが本当に 「自分を生き」て、そうして自分を「生き切るために」に解き放たれなければならない鎖とは。言葉だけの自由や人権を、わたしは信じない。

プロフィール 1945年栃木県宇都宮生まれ。終戦を迎える年に、そして民主主義のスタートに偶然生まれたことを、必然に変えたいと思い、生きてきたような。22歳でラジオ局入社。メディアというものが、いかに自分たちは一般の市民とは違うのだという「選民意識」によって成立しているかを痛感。ほぼ10年で退職。著書の印税をもとに、子どもの本の専門店「クレヨンハウス」を設立。来年は50周年。
1980年代から小説『ザ・レイプ』、『セカンド・レイプ』、「セクシュアル・ハラスメント」など、女性の視点で性加害を描きつつ、社会におけるマイノリテイの「声なき声」をテーマにした作品多数。他にも『母に歌う子守歌』、『老いることはいやですか?』、『明るい覚悟』、『わたしたち』など多数の著作。
※報道関係者による取材申し込みに関しましては、事前に教科研事務所まで連絡をお願いいたします。
☆クレヨンハウスHP https://www.crayonhouse.co.jp/shop/default.aspx
クレヨンハウスは成蹊小学校の近くです!ぜひお立ち寄りくださ い。
教科研講座 対面のみ
8月6日(水)10時~12時
大会初日の午前は、多彩な教科研講座で教育と文化の視野を広げましょう!
| 講座 | 内容 | 世話人 | |
| 講座1 | 私の教室物語から始めよう-コンシャスネス・レイジング | 「あの子が立ち上がってお話に来た」喜びが「立ち歩きを止められない」指導力不足の評価になる。モヤる。The personal is political.おしゃべりして考え合いましょう。 | 菅野真文(北海道) 石本日和子(兵庫) |
| 講座2 | 哲学対話で教育学入門 | 哲学対話で考え議論する、教育実践者のための教育学入門講座です。専門知識は不要、教師以外の方も大歓迎。講師は神代健彦常任委員(京都教育大学)。 | 神代健彦(京都) 寺尾昂浩(神奈川) |
| 講座3 | 対話と学びが広がる教室 | 学級経営のためのファシリテーションの具体的な姿を紹介します。安心して学ぶ場としての教室を創造していきたいです。講師は小学校教諭の薮内恵さん(ホワイトボード・ミーティング®認定講師)です。 | 増田陽 (東京) |
| 講座4 | 読書のアニマシオン~言葉を楽しむ・言葉に流されない | 読書のアニマシオンは、仲間とワイワイ楽しみながら広い本の世界へ誘います。①国語辞典で楽しもう(岩辺) ②SNSのアニマシオン(笠井)を通して案内します。 | 笠井英彦(静岡) 泉宜宏 (東京) |
| 講座5 | 戦後80年と現代 | アジア・太平洋戦争の見方がこの80年でどう変わってきたのか。今後の課題としては何があるかを皆さんと語り合いたいと考えています。 | 金 竜太郎(東京) 新東一樹(山梨) |
| 講座6 | アメリカの政治経済はどこへ向かうのか | トランプ政権発足によって世界は不安に包まれています。どんな展望のもと諸政策を展開しているか、またその条件はなにか、学びたいと思います。講師は森原康仁さん(専修大学)です。 | 中村清二(東京) 金馬国晴(神奈川) |
| 講座7 | 食育は無限の可能性を秘めている | 給食の向こう側を想像したことがありますか? 食の窓から世界と日本の社会を見てみよう! 食を教科・領域とつなげば、子どもたちの学びは無限大に! | 富田充保(神奈川) 千葉春佳(東京) |
| 講座8 | あそびを通して子どもの権利を考える! | 三鷹を拠点として活動する「NPO法人 あそび環境Museum アフタフ・バーバン」による子どもの権利条約ワークショップです。大人も子どもも関わりながら遊びながら、それぞれの思いを表現しながら「子どもの権利」について考えあいましょう。 | 福家珠美(神奈川) |
<第2日 8月7日(木)>
分科会 対面・オンライン併用
9時30分~17時
*番号に◎がついている分科会は対面のみ。
*第12分科会「地域と教育」は休会
*第18分科会「教室と授業を語る」は教育問題フォーラムBで開催。
| 分科会 | テーマ | 内容 | 世話人 | |
| 合同1, 16 | 子どもの生活と文化 現代の子育てと親・おとな | 今を生きる子どもの声と姿 | 〇現代社会は子ども本来の育ちを保障しているか 〇子どもへの要求はかれらの自由を奪っていないか 〇今を生きる子どもの声と姿から現代の子ども観を問い直す | 泉 宜宏(東京) 新東一樹(山梨) 石本日和子(兵庫) 渡邉由之(大阪) |
| 2 | 青年期の教育 | 公教育の解体に抗し、学校内外に豊かな青年期の教育を | ○学生のリアルに触れる大学教育 ○青年期に向きあう高校教育の実践 ○地域で若者を支え、育てる | 児美川孝一郎(東京) 南出吉祥(岐阜) |
| 3 | 能力・発達・学習 | 強いられた主体性と子どもの発達 | 〇学習指導要領にみられる新自由主義の具現化 〇枠のなかで主体性を強いられる子どもと教師 〇単色の有能さや主体性ではない豊かな発達のあり様を考える | 神代健彦(京都) 前田晶子(神奈川) |
| 4 | 身体と教育 | 人類の進化・進歩と「からだづくりと認識」 | 〇地球規模の自然環境変化と人類の観点から 〇コミュニティと人類の観点から 〇デジタル化と人類の観点から 〇養生・保養観と人類の観点から | 山本晃弘(神奈川) 野田 耕(福岡) |
| 5 | 美的能力と教育 | 小学生の今を受け止めながら表現の可能性を拓く | 〇一人ひとり異なる子どもたちの表現を拓く図工の3年間 〇目の前の子どもの姿に呼応する脚本づくりと劇活動 〇参加者による多様な表現活動の実践紹介と交流 | 落合利行(東京) 山田康彦(三重) |
| 6◎ | ことばと教育 | 主体的な学びをつくることばの教育 | 〇ことばの豊かな発達とコミュニケーション 〇ことばを育てる国語・外国語の授業 〇生活に根ざして紡ぐ自己表現活動 | 瀧口 優(東京) 神 郁雄(東京) |
| 7 | 社会認識と平和 | 社会科授業の発展を目指して | 〇社会科系科目の学習指導要領改訂をめぐる論点整理 〇地球市民を育てる歴史教育実践 〇ICTを活用した地理教育実践 〇主権者を育てる政治教育実践 | 池田考司(北海道) 一盛 真(鳥取) |
| 8 | 自然認識と教育 | 「自然を不自然と感じる」子どもの認識課題を考える | 〇“自然離れ“と子どもの自然認識の発達課題を探る 〇子ども・青年の自然認識を育てるカリキュラムと実践課題を探る 〇成蹊小学校内での自然散策 | 伊東大介(東京) 三石初雄(東京) |
| 9 | 道徳性の発達と教育 | 子どもの〈食〉から考えるケア・倫理・共同性 | ○「道徳と教育」部会のあゆみ~自主性、人権、そして子どもの生活へ~ ○「こども食堂」に集う子どもと大人 ○中学社会科で食と動物福祉を学ぶ | 櫻井 歓(東京) 田口和人(群馬) |
| 10 | 教育課程と評価 | 公教育における多様で豊かな学びと教育課程の創造 | 〇学習指導要領の改訂動向を見すえて 〇公立学校(小・中・高)での学びと教育課程 〇きのくに学園での実践 〇NPOと学校が協働して行う学びづくり | 梅原利夫(東京) 菅間正道(埼玉) |
| 11 | 学校づくり | いまを生きる子どもと共に学校をつくる | 〇東京の子ども、学校の現在 〇福祉現場から見える子どもと家族、学校の姿 〇子どもが主人公となる教育課程と学校をつくる | 田沼 朗(東京) 三橋勝美(埼玉) |
| 13 | 政治と教育 | 子ども・若者を取り巻く政治と社会の困難に向き合う | 〇改めて「新自由主義」と教育を問う 〇学びの多様化と教育の公共性 〇主権者教育と社会構造への視点 | 中田康彦(東京) 寺尾昂浩(神奈川) |
| 14 | 性と教育 | 子ども・若者の権利と性 | ○子ども・若者の性をめぐる現状 ○権利としての性の学び ○総括討論 | 中嶋みさき(埼玉) 横井夏子(栃木) |
| 15 | 発達障害と教育 | 子ども理解の深化と自己の育ちを支える実践の追求 | 〇一人ひとりの願いや困難、教師・援助者や家庭への理解を深める 〇子ども・青年の「自己の育ち」を支える教育実践のあり方を探る | 加茂 勇(新潟) 小池雄逸(東京) |
| 17 | 教師の危機と希望 | 教師のやりがいと専門性を考える | 〇いま教師と学校がおかれている現実を確かめる 〇「日々の苦労とやりがい、そして教師としての生きがい」を語り合う 〇実践報告を通して教師の専門性を考える | 山﨑隆夫 (東京) 霜村三二(埼玉) |
<3日目 8月8日(金)>
教育問題フォーラム 対面・オンライン併用 8月8日(金) 9時30分~12時
| フォーラム | 内容 | 世話人 | |
| A | 学習指導要領改訂の動向と教育課程 | 次期学習指導要領改訂は、教育の目標・内容だけでなく、学校の制度や形態も焦点にしています。改訂の動向を見据えつつ、子どもの願いと要求に応える教育課程を展望します。 | 本田伊克(宮城) 久保田貢(愛知) |
| B | springbord! 〜 教科書「が」教える授業を超えて | 教科書をバネ(springbord) として、子どもの学びが飛躍する授業を紹介しながら、授業をつくることの楽しさを考えます(教室と授業を語る分科会企画)。 | 石垣雅也(滋賀・北海道) 村越含博(北海道) |
| C | 学校と地域、コミュニティスクールとはなにか。 | 学校と地域の連携は、学校、地域によって異なります。三鷹市で一つの小学校と連携する「夢育支援ネットワーク」の20年の活動から、可能性と課題を探ります。 | 荒井文昭(東京) 本山 明(東京) |
| D | 教育系NPOと公共性のゆくえ | 教育の公共性を考える際、公教育の周辺で活動する「教育系NPO」の存在が大きくなっているが、単純な是非論を超えて、実践的協同を進めていく回路を探ります。 | 南出吉祥(岐阜) 寺尾昂浩(神奈川) |
| E | リベラルな私学が抱える課題 | 子どもの人権や自由を尊重し貴重な実践を創ってきたリベラルな私学が、教育の継承や生徒募集で困難に直面しています。私学の課題と展望について交流します。 | 田沼 朗(東京) 米山昭博(東京) |
| F | 学校の「男性性」を問う | 『学校の「男性性」を問う』が教科研編で出版されます。執筆者が、学校の「男性性」を語り、ジェンダー平等と子どものからだ(命)を大切にする教育を皆さんと一緒に考えます。 | 菅野真文(北海道) 石本日和子(兵庫) |
| G | 気候変動と教育 | 深刻な気候変動が地球規模で進行している現在、教育になにができるでしょうか。本フォーラムでは、諸外国の事例から私たちが取り組むべき課題を考えます。 | 神代健彦(京都) 大日方真史(三重) |
| H | 自然災害と子ども・教育 | 『教育』5、8月号で、能登半島地震と被災経験の継承、防災を取り上げました。関連する理論や実践、経験を交流するなかで、災害との向き合い方を考えます。 | 山沢智樹(岩手) 新東一樹(山梨) |
| I | 多摩の戦跡から学ぶ戦争と平和、いま平和教育をつくる | 中島飛行機多摩工場爆撃を素材に、戦争の記憶をどのように平和教育を通して継承していくのかを考えます。特に既存の歴史が、戦後つくられたものではないかを問い返し、教材化するうえでの注意点を考えます。 | 一盛 真(鳥取) 杉田明宏(東京) |
おわりの集い 対面・オンライン併用
8月8日(金)13時~15時
シンポジウム 「不登校問題を考える」
(詳細は、企画中)
宿泊・昼食
各自でご用意ください。都内のホテルは早めにご予約ください。
キッズルーム 申し込み締めきり7月22日
[対象]3歳~小学生
※参加申し込み後に配信されるグーグルフォームから申し込みください。
詳しくは問い合わせ先まで。
申し込み
Peatixを利用して、6月中旬、申し込み開始予定です。
問合せ先
教育科学研究会
〒162-0818 東京都新宿区築地町19小野ビル2階
Tel&Fax:03-3235-0622
E mail:kyoukaken@nifty.com
※電話受付:金13:00~17:00
