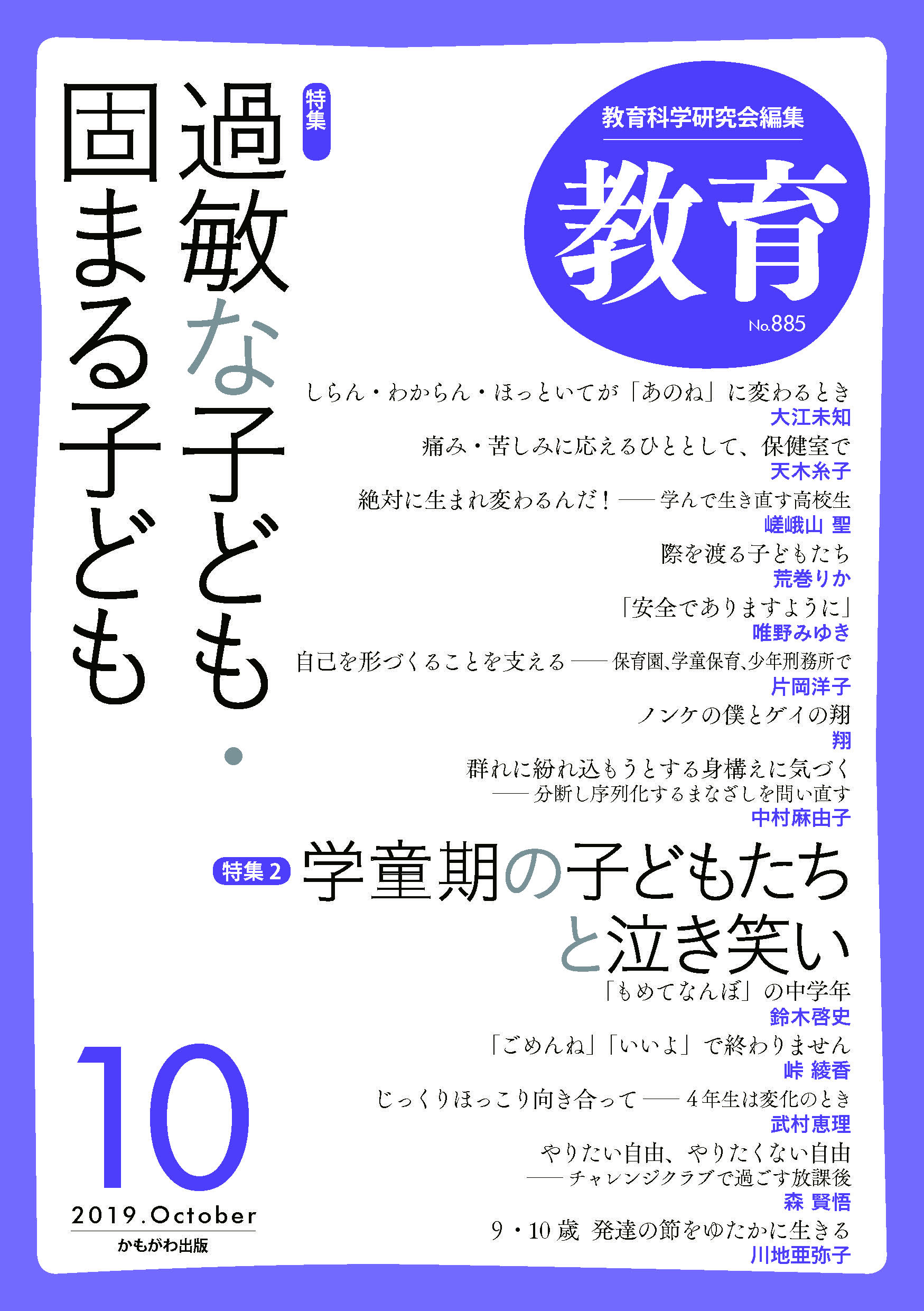
月刊誌『教育』 2019年10月号
- 特集1
- 過敏な子ども・固まる子ども
- 特集2
- 学童期の子どもたちと泣き笑い
- とびらのことば
- みんなちがって生きること
定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。
*定期購読のおすすめ*
定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB
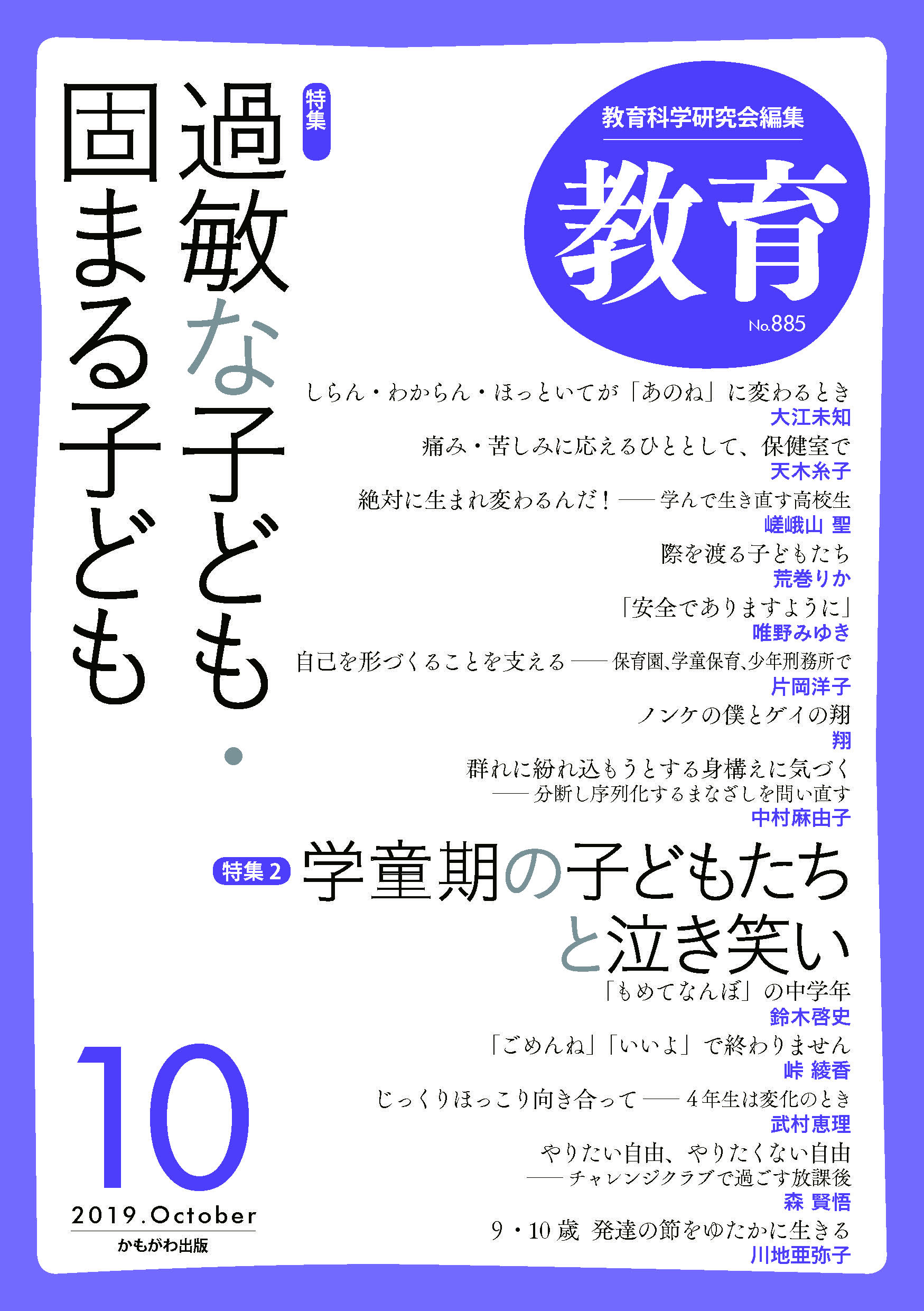
定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。
*定期購読のおすすめ*
定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB