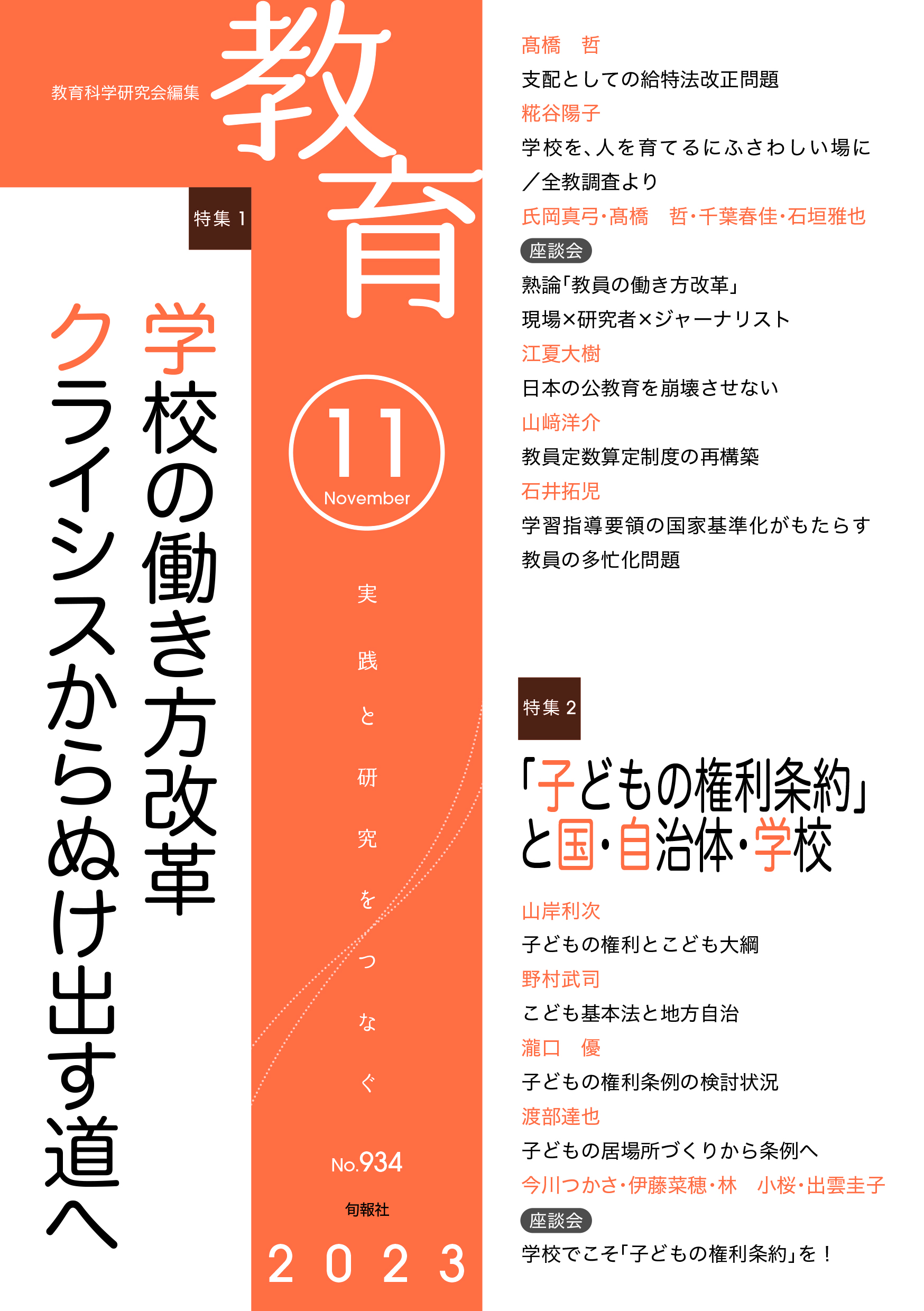
月刊誌『教育』 2023年11月号
- 特集1
- 学校の働き方改革 クライシスからぬけ出す道へ
- 特集2
- 「子どもの権利条約」と国・自治体・学校ーーこども基本法・こども家庭庁始動の中で
定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。
*定期購読のおすすめ*
定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB
目次
特集1 学校の働き方改革 クライシスからぬけ出す道へ
特集2 「子どもの権利条約」と国・自治体・学校ーーこども基本法・こども家庭庁始動の中で
シリーズ
特集 とびら
【特集1】
