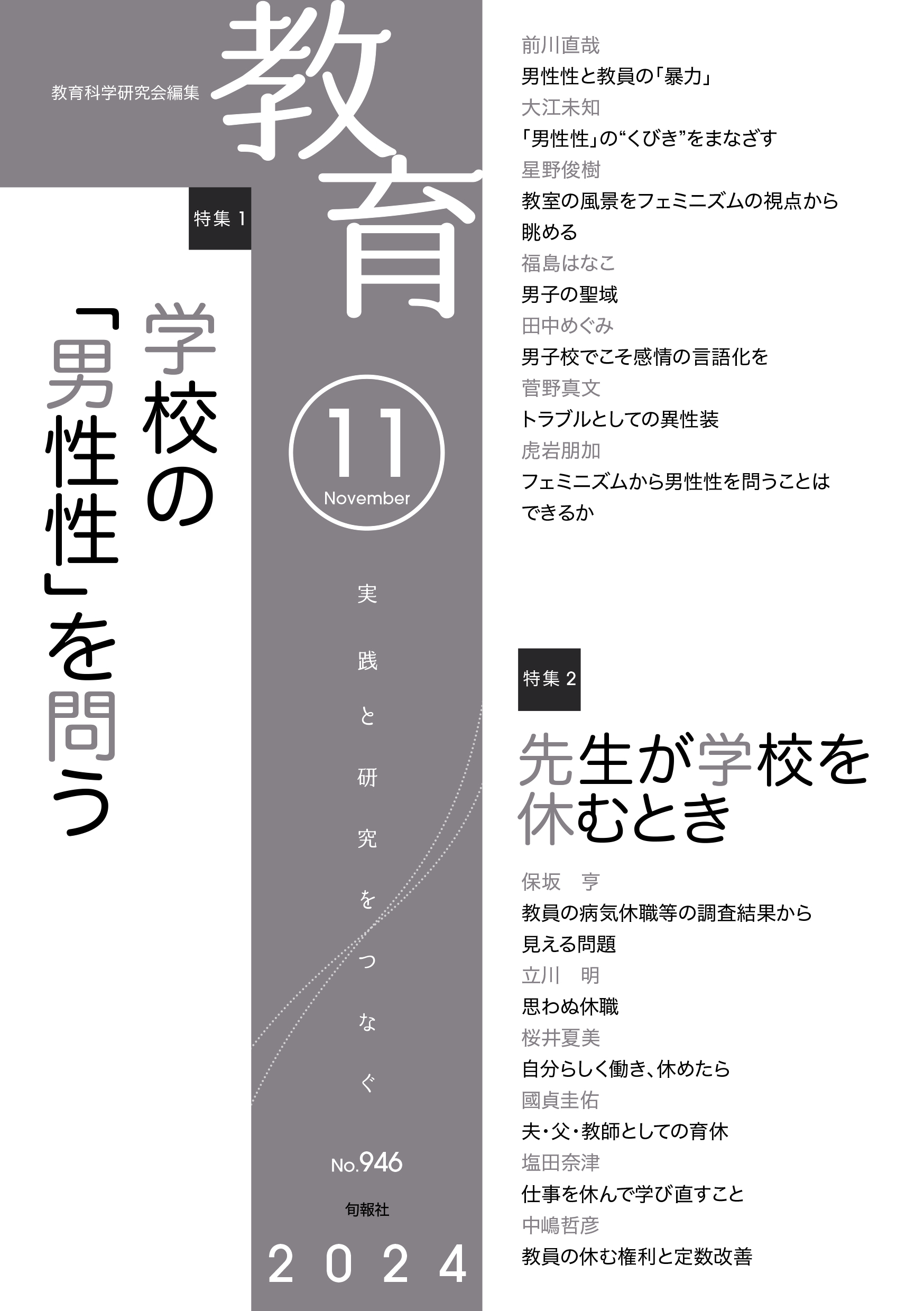
月刊誌『教育』 2024年11月号
- 特集1
- 学校の「男性性」を問う
- 特集2
- 先生が学校を休むとき
定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。
*定期購読のおすすめ*
定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB
目次
特集1 学校の「男性性」を問う
特集2 先生が学校を休むとき
シリーズ
特集 とびら
【特集1】
