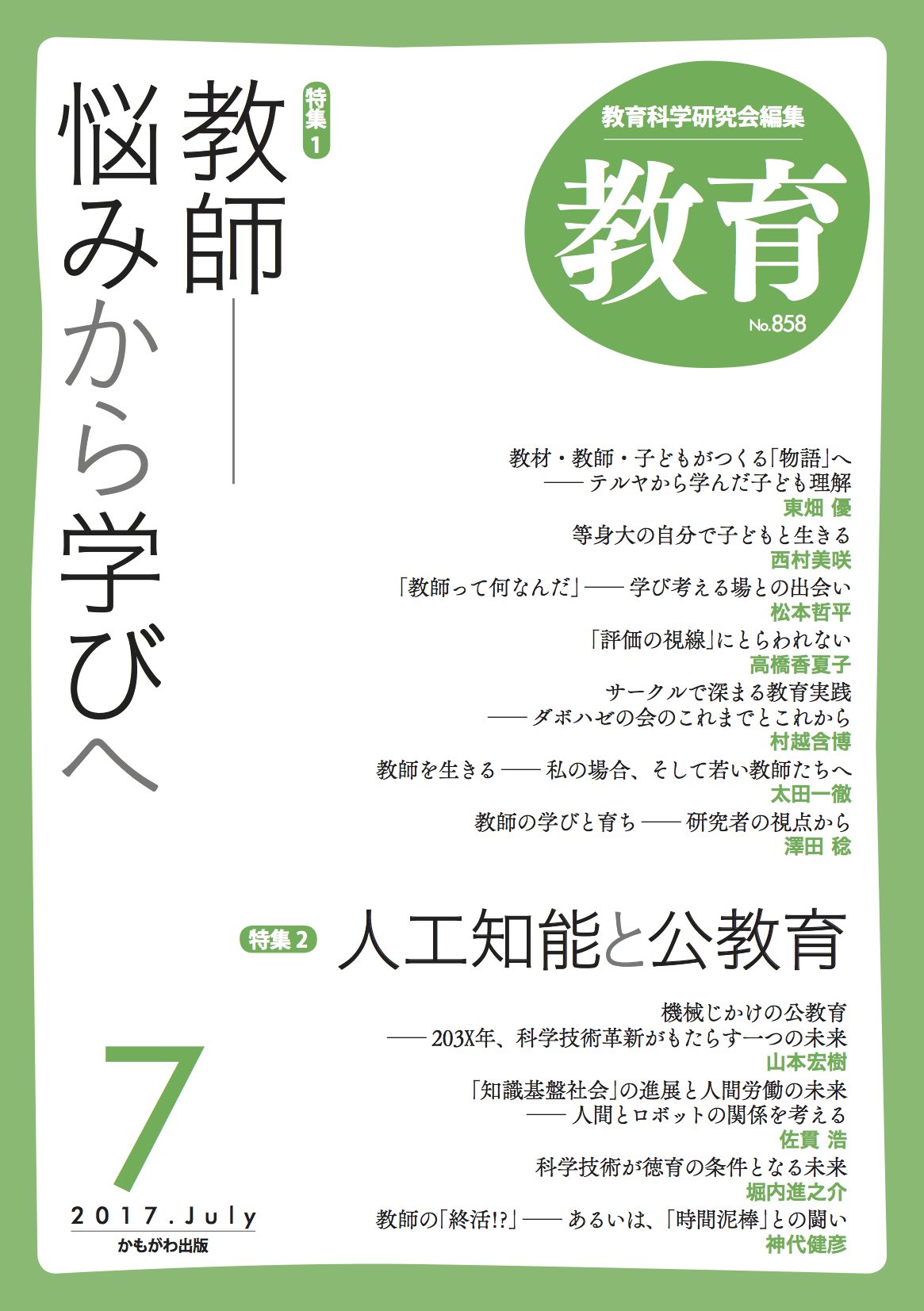
月刊誌『教育』 2017年7月号
- 特集1
- 教師――悩みから学びへ
- 特集2
- 人工知能と公教育
- とびらのことば
- 教師としての学びと育ちの物語を考える
定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。
*定期購読のおすすめ*
定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB
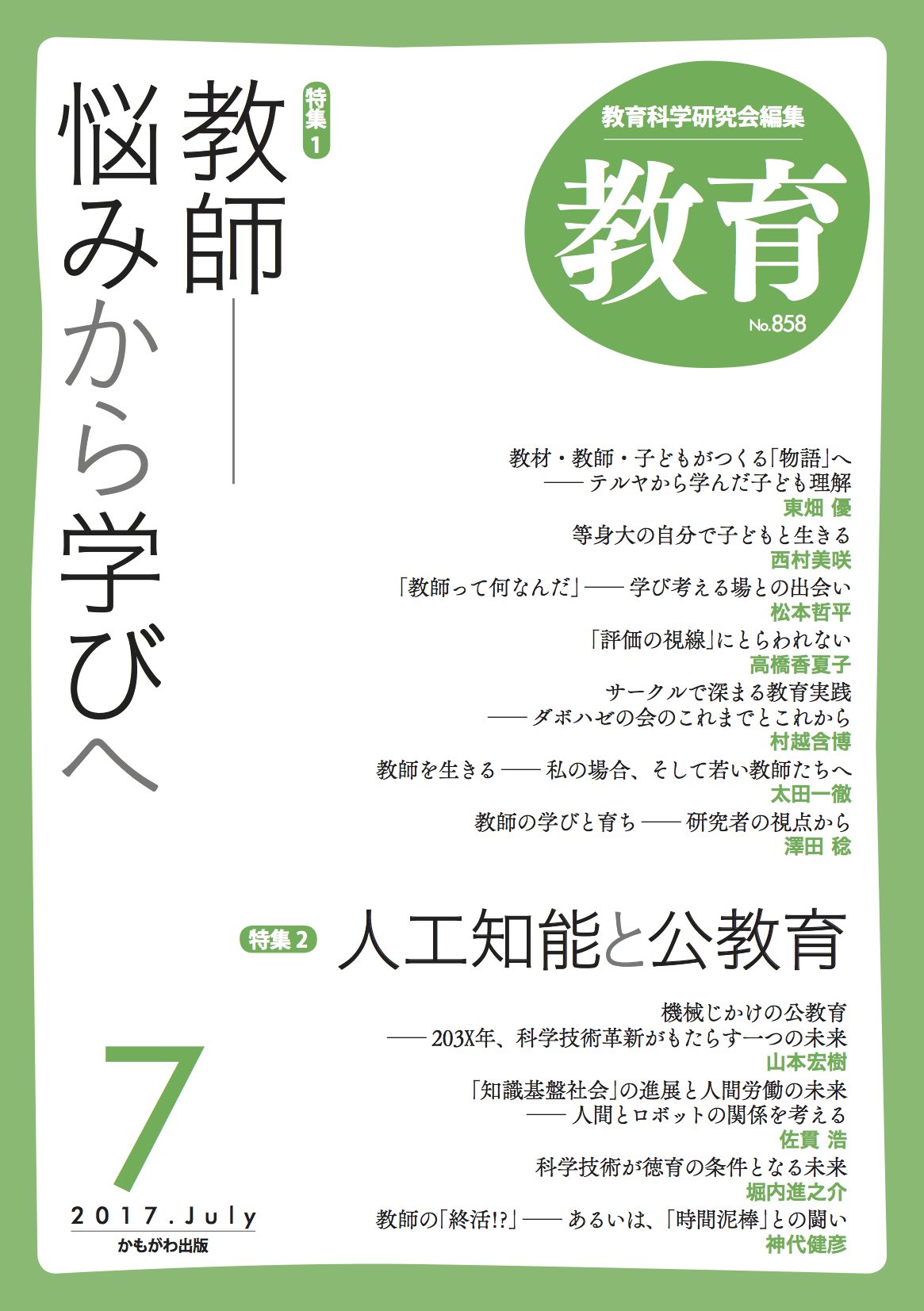
定価990円 / 各号、書店/インターネットにて販売中。
*定期購読のおすすめ*
定期購読やバックナンバー購入については旬報社のサイトをご覧ください→旬報社WEB